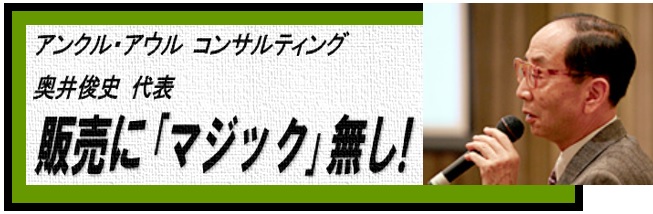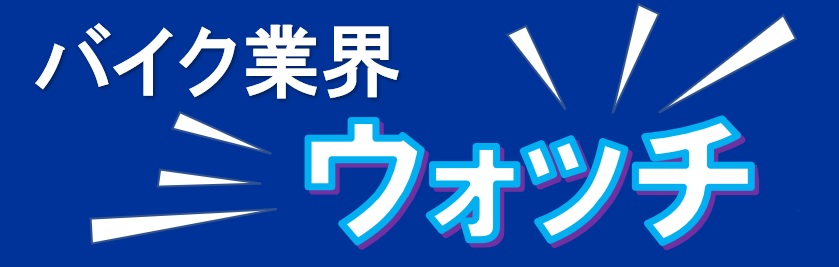日本自動車輸入組合は7月30日、都内で定例記者会見を開き、ゲルティンガー剛・理事長が今年の上半期の輸入車販売実績と下半期の販売展望、同組合の主要活動とする市場活性化、環境・エネルギー分野、安全と基準の調和、自動車公正取引・アフターセールス分野、二輪の進捗状況などについて取り上げた。
今年の上半期の輸入車販売実績を振り返り、国内自動車市場は登録台数が約150万台で、上半期としては2年ぶり前年を上回りました。このうち外国メーカー車の登録台数も前年同期比で7.3%増の12万2165台で、2023年上半期以来2年ぶりに前年を超えたとした。
電動車のEVでは輸入は堅調で、2024年11月以降8ヵ月連続で増加。上半期の輸入EVの登録台数は、前年同期に比べ31.6%増の1万4191台と15,000台に迫る勢いであった。2020年上半期以降6年連続で上半期過去最高の台数を更新し、2025年6月には外国メーカー車に占めるEVのシェアも単月として最高の14.6%に達したと強調。
こうした実績は、政府による切れ目ない継続的な補助金などの各種支援策や、JAIA会員各社がニーズにこたえられるよう、積極的にEVの製品構成を拡充してきたことを理由に挙げた。
輸入EVのラインナップは、2020年には10ブランドで20モデルであったが、今年6月末時点には商用車も含め22ブランドで173モデルにまで拡大した。多種多様なEVモデルが投入され、輸入車がEV市場で積極的な役割を果たしてきたことで、充電インフラなど電動化に関する課題について同組合でも具体的に取り組みを進めており、着実に検討課題が解決の方向に進んでいるなどとした。
下半期の展望については、輸入車市場は引き続き堅調に推移するとみており、上半期に発売された新型車が引き続き市場をけん引、下半期にも会員各社が引き続き魅力的なニューモデルを投入し、市場の活性化を進めているとした。秋から2026年初めにかけて東京を始め国内各地域でジャパンモビリティショーの開催予定や、各地で地方輸入車ショーの開催も予定され、各社より様々な新型モデルの発表と投入を控えていることから、自動車市場全体の盛り上がりが期待されているとした。
特に輸入EVでは、税制優遇や補助金支援の継続もあり、東京都をはじめ各自治体にも支援が広がっていることに加えて会員各社が積極的に日本市場へ輸入EVを投入していくことで、引き続き販売台数は着実に増加していくとみており、年間では初めての3万台を超えも見込む。輸入EVは堅調に推移し7年連続で前年実績を上回ると期待を寄せている。

左より入野泰一・副理事長兼専務理事、ゲルティンガー剛・理事長
主な活動では引き続き、市場活性化と環境・エネルギー分野に関する活動として、電動車をさらに普及させるために、補助金制度などに関する政府への要望活動、電動車の普及促進イベント開催、充電電圧などに関する規制緩和の検討を含む、充電インフラの環境整備、リチウムイオンバッテリーのリサイクルを主軸に事業を進める。
欧州では2024年のBEVシェアは13.6%で、世界全体では今年の自動車販売の4台に1台がEVかPHEVになるとの予測もあるとしており、日本は2024年のEVシェアは1.6%、PHEVと合わせて2.8%で、世界の市場に比べ割合が低いことから、補助金による支援は引き続き重要であり、今後も継続的な補助金施策を政府に働きかけていくとしている。こうした取り組みで日本のカーボンニュートラル促進に貢献するため、積極的なEVの投入を継続していく。
輸入EV車の認知向上では、今年度11月のJapan Mobility Showや、12月の大阪モーターショーなどの自動車関連イベントとの連携も視野に入れ、さらなる工夫を凝らし、周年イベントとしても位置付け、JAIAならではのイベント開催に向けて企画・検討を進めていく考え。
具体的には、今年11月中旬から下旬ごろに、関西地域で輸入電動車の魅力をさらに理解して頂くためのB to Bイベントの実施を検討している。今年度予定のイベントでは、輸入電動車の認知向上を高める活動から、カーボンニュートラルに加えて、 安全運転なども寄与する。このためGX・ DX(自動運転)も意識したイベント開催で、GX・DXを実現していくとしている。
電動車の普及において、ドイツ並みの高電圧充電の実現に向けた取り組みを進めており、昨年10月には高電圧化に向けた制度改正が実現した。
今年5月、JAIA賛助会員であるe-Mobility Powerと東光高岳が共同開発した400kWクラスの急速充電器が初公開され、今年度中に高速道路に配備されることで、充電環境は大きく変わることを挙げた。400kWクラスの充電器車両なら15分もかからず充電ができるようになるとして、充電インフラの環境整備の課題解決には関係事業者の協力が不可欠で、今後とも賛助会員との連携を強化していく方針。
充電設置にかかる費用の増額に対する政府の補助金、集合住宅の充電環境、急速充電器の公道への設置およびサービスステーションにおける充電インフラのさらなる整備などを呼びかけた。加えて、新築戸建てや集合住宅への充電器設置義務化の流れが、東京都のほかに地方に展開されることも重要と指摘し、同組合では地方自治体との連携を積極的に進めいく考え。
リサイクル分野では、電動化の推進に必要不可欠な、リチウムイオン電池のリユース、リサイクルについて、国内自動車メーカーも含めた駆動用バッテリーの共同回収システムに参加する会員が着実に増加しているとした。引き続き、電池リサイクル関連事業者との意見交換を進め、会員各社が業界の最新情報を随時把握し、適切に車載用蓄電池の回収に対応できるように組合が支援していく。
税制改正の要望では、現在のエコカー減税の期限である今年度末までに、自動車関係諸税の抜本的見直しが行われる予定とした。同組合が要望した車両取得時の環境性能割の廃止の意見に対しては、昨年末にまとめられた与党税制改正大綱で「取得時における負担軽減等、課税のあり方を見直すとともに、自動車の重量及び環境性能に応じた保有時の公平・中立・簡素な税負担のあり方」について結論を得ると明記されたことを挙げ、組合としては実現に向け、一層要望活動を進めていくとした。
特に電動車の普及を加速する必要がある中で、ユーザーの負担増につながる制度改正は避けるべきであり、低炭素化の大きな効果が望める電動車を含む重量車両への過度な税負担は避けるべきであり、BEV、PHEV、FCEVなど電動車の普及を加速させるための税制改正を政府に対して働きかける。また、バスやトラックなどの商用車の電動化や水素の活用も重要であることから、昨年に引き続き要望を盛り込んでいきたいとした。
安全と基準の調和に関する活動では、引き続きJASICの活動を通じて、車両法規の国際的な調和がより一層推進され、より完成された利用価値の高いIWVTAが早期に実現するための活動を行っていく。残された日本の独自要件が国際調和などにより解消されるように活動していく。
さらに、車両の基準適合性確認に係る認証手続きにつきましては、一昨年JAIAより車両認証手続きについての合理化・効率化を国土交通省へ要望し、今年3月にJAIAの要望がある程度反映された手続きの見直しが実現されたことを挙げた。
同組合では残存要望を含めて、今年6月にはさらなる車両認証手続きの簡素・合理化要望を国土交通省に提出し、引き続き国土交通省など議論を重ね、輸入車両の安全・環境保護性能を担保しつつ、必要な合理化・効率化が実現するよう活動していくなどとした。
自動車公正取引・アフターセールス分野などの活動では、会員への自動車公正競争規約の周知徹底および、公正な取引の確保を目指した活動を引き続き進める。アフターセールス分野では、法令を遵守した自動車の点検・整備やリコール関連手続きの実施等、会員各社が適切に対応できるよう対処していく。
整備人材の不足の課題では、緊急の対応が求められており、2022年に自動車整備人材関連情報連絡会を設置し、課題克服に向けて、各種情報の共有を含め会員各社と具体的な活動を続けており、今年度は自動車整備学校との連携、グローバル人材、オールジャパンでの取り組みの3点を念頭に四輪・二輪が連携して活動を展開。
モーターサイクル
主要活動の第5の柱とする、モーターサイクルの活動については、今年の上半期における輸入小型二輪車の新規登録台数は、1万2469台で前年同期の1万3930台と比べ10.5%減少し、6期振りの減少であったとした。下半期の見通しでは、販売実績が順調に推移することを期待するなどとした。
活動の柱とする「市場活性化のための活動」では、過去の全開催の後援を付与した名古屋モーターサイクルショーは、今年も4月に第4回を愛知県国際展示場で開催。高校生以下と女性の入場料を無料にし、モーターサイクルのすそ野を広げる施策が行われたとした。主催イベントとして、同月には10回目の節目を迎えた輸入二輪車試乗会を開催し45媒体134人の報道関係者が参加。今後も、主要都市での同様の企画に積極的に参加し、カーボンニュートラルへの取組も進めていことした。
9月19日に「第13回 BIKE LOVE FORUM in 埼玉・おがの」が埼玉県小鹿野町で開催予定であり、モーターサイクルの将来について政府や業界等関係者による議論が行われ、環境整備のさらなる進展に向けた有意義な意見交換の場になることが期待されるとした。
二輪車について高速道路料金の独立化や二輪駐車場の拡充、二輪免許制度の見直しを継続的に要望していく考えで、同フォーラムなどを軸として他団体と連携しながら、政府・各政党のオートバイ関連のプロジェクトチーム検討会の場などにおいて、高速道路料金区分の独立化と料金適正化に向けた要望活動を実施していくとした。
二輪活動でも、規制の国際調和を図るための活動、さらなる輸入モーターサイクルの普及と国内二輪市場の活性化に取り組んでいくなどとした。
モーターサイクルでの質疑応答では、今年上半期には6期ぶりの減少し、主にハーレーダビッドソンの販売が影響したことについては、前年同期が高水準であったほか、一部会員メーカーが減少したことが要因。下半期は順調な販売を見守りたいとした。
公正取引委員会により一部の輸入元が優越的地位の濫用に該当するといった報道もあり、こうした輸入元での優越的地位の濫用などを同組合で防止、是正についての質問では、個社についてのコメントは控えるとした上で、同組合では自動車公正取引協議会から講師を招き、JAIA会員や広告代理店も含めて、公正競争規約の順守の徹底などに向けた研修会を実施している。引き続き、自動車公正取引協議会と連携しながら勉強会などを含め各社の認識を管理できたらいいと考えるとした。