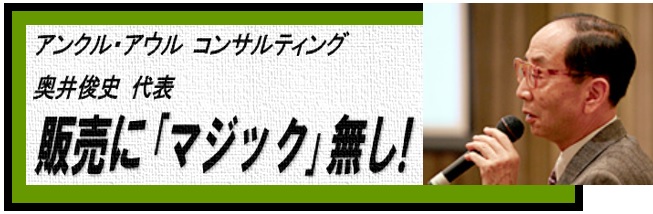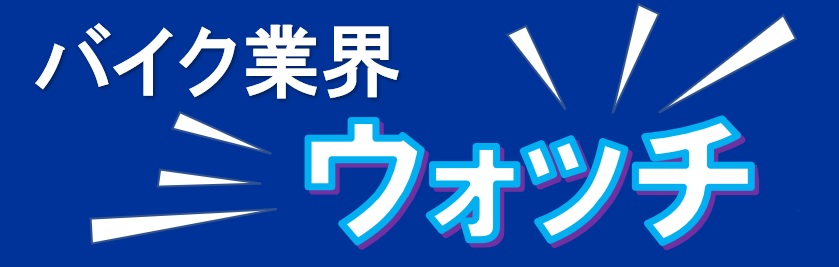ホンダは1月下旬、二輪事業の説明会を開き、2024年は37の市場で過去最高を上げたとしている。今後は人口増加が見込める南西アジアや中南米などで販売拡大を見込んでおり、現在の5000万台から2030年には電動を含めて6000万台規模、世界シェア5割に引き上げる。電動二輪では特にインドでシェア1位を目指すほか、28年にはインドで電動二輪車専用工場を稼働させるなど、インドを中心に製販で強化する。
創業以来で累計生産台数は5億台達成が視野に入ったとしている。今年3月までの2024年度の販売台数も、世界市場でシェア約4割となり2020万台を見通す。特にインド、インドネシア、タイ、ベトナムなどのアジアでの販売台数が全体の85%の1717万台、日本や欧州、米国は6%の120万台で昨年の2024年では37の市場で過去最高を上げたとする。
二輪事業の今後の展開では、将来的に人口増加や所得向上が見込めるグローバルサウスと呼ばれる、南西アジア、インドネシア、フィリピン、ブラジルなどの中南米などで販売拡大意を見込んでいる。これにより現在の5000万台から、2030年には電動車を含め6000万台規模の成長を見通す。長期的には電動車を含め世界シェアを5割に引き上げ取り組むとしている。
【コミューターモデル】
日常の移動手段となるスクーターなどのコミューターモデルの拡販では、最大市場となるインドで、通勤などの移動利用される最量販スクーターをはじめ、若者向けスクーター、小排気量のモーターサイクル、高付加価値のライトモーターサイクルなど、市場ニーズに合わせて製品構成を拡充。インドでの販売網やサービスの拡充のため販売施策も強化し、市場シェアナンバーワンに手が届くところまで拡販していくとしている。
生産でも体制でも強化を進め、インドでの競争力ある製品はインド市場に止まらず、中南米などへも輸出し効率的な製品展開を行う。アセアン各国やパキスタン、バングラディシュ、ブラジルでは労働人口の増加による経済成長が見込め需要拡大を狙う。
【大型FUNモデル】
趣味としての大型FUNモデルでは、需要が高い欧州で、CBやCBR、アフリカツイン、レブルなどの各シリーズで魅力向上に継続的に取り組むほか、「ホーネット」「トランザルプ」などのモデルを復活し投入した。ライディング体験の質の向上につながるディアル・クラッチ・トランスミッションやホンダ・イークラッチといった最新技術を採用した「操る楽しさ」を備えた製品を拡充した。この結果、2024年は欧州主要5カ国でシェアナンバーワンを獲得したとしている。
大型モデルでは多品種・少量生産のため車両のプラットフォームの共通化を進め、開発から調達、生産の効率化に取り組んだ。
一方で、すでに発表した二輪車で初となる「電動過給機」搭載のV型3気筒エンジンを搭載させたモデルの量産化に向けた開発を行っていると、近い将来、同エンジン搭載モデルの投入を示唆する。
これらの取り組みで2018年度時点での二輪事業の収益の多くはアジア市場に偏っていたが、2023年度には欧州などの先進国、南米などでも拡大したことで、各市場でバランスよく収益を獲得でき全体での収益増加、事業体質も向上したことを挙げる。
【カーボンニュートラル】
2040年代にすべての二輪製品でカーボンニュートラル実現を目指す。環境戦略として二輪の電動化を加速させる。商品ではすでに発表に通り2030年のグローバルでの電動二輪車の年間販売台数目標を400万台、30機種の電動二輪車の投入を目指す。2030年までの投資金額は約5000億円の予定で、達成に向け今年2024年を電動二輪車のグローバル展開元年と位置付け、本格的に取り組む。
昨年10月にはインドネシアで交換バッテリー「Honda Mobile Power Pack e:」(モバイルパワーパック イー)搭載した「CUV e:」、固定式バッテリー搭載の「ICON e:」を発表した。CUV e:は今後、欧州や日本を含む20ヵ国での販売を予定。昨年11月にはインドで「ACTIVA e:」、固定式バッテリー「QC1」を発表しこれまでの13機種を投入し、30機種投入の計画を着実に進めた。また、スポーツモデルでも「EV Fun Concept」、都市型モビリティ「「EV Urban Concept」を公開し、多様化するニーズにこたえる製品構成で電動二輪車でも主導的な地位を目指す。
電動二輪車のインフラでは、日本やインドネシア、タイに続きインドでも交換バッテリー搭載モデルの普及に向け、現地法人によるバッテリーシェアリングサービス事業を展開。ベンガル―ル、デリー、ムンバイの3都市でシュエリングサービスを開始。インドでは全土に6000店で展開している業界最大とする販売網を活用し、アフターサービスなどの強化と、今後投入する固定バッテリー搭載車の電欠不安に対しても販売網をいかして充電網を拡充し、インドでのシェアナンバーワンを目指す。
一方、電動二輪車の導入で課題となるTOC(総保有コスト)の低減では、3年間保有した際にかかる総費用が、エンジン搭載車と同等になる価格帯での販売を目指し、2028年にインドで電動二輪車専用工場を稼働させる。
他方、燃費改善によるCO₂削減に加え、ガソリンやエタノールなどの混合燃料に対応するモデルを、ブラジルで導入実績のあるフレックスフューエルモデルの適用地域を拡大。インドで他社に先駆けフレックスフューエルモデルの「CB300F」を投入する。
生産でも熊本製作所で太陽光発電やリチウムイオン蓄電池の導入で従来の電力使用量を削減や、ブラジルでの森林保全、環境にやさしいバイオエンジニアリングプラスチックの適用拡大、リサイクル素材の二輪製品への利用なども進める。